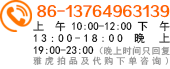商品参数
- 拍卖号: r1135847044
开始时的价格:¥100 (2000日元)
个数: 1
最高出价者:
- 开始时间: 2024/5/10 13:24:17
结束时间:
提前结束: 有可能
商品成色: 二手 - 自动延长: 会
日本邮费: 中标者承担
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

■■画像ー1・・・■■
●●「天目へ入門」・・・●●
**”監修=竹内順一(東京芸術大学美術学部教授)”**
★室町時代・時の権力者たちは中国から海を越えて渡ってきた美術品を・「唐物」・として愛し・その収集に
力を注ぎます。天目もそのひとつ。唐物は莫大な数にのぼり・吟味され・格付けされ・整理され・その集大
成が座敷飾りの故実書・『君台観左右帳記』・に結実します。天目の分類の範となった・この巻子から・「
天目とは何か」・を探ります。
◆「曜変天目」・(国宝・静嘉堂文庫美術館)。
●●「天目の三条件」・・・●●
◆1・すぼまってから外に反る鼈口。
◆2・漏斗状に開いた腰部。
◆3・胎土を露わにした低い高台。
●●「天目とは形のこと」・・・●●
★天目という器だけでは未完成なもの。天目台に載って・初めて完成した姿となる。
◆「灰被天目」・「尼崎天目台」・(徳川美術館)。
■■本ー画像・・・■■
●●「天目は七種に分けられていた」・・・●●
★『君台観左右帳記』・では・現在・天目と呼びならわしているものをまとめて・「土之物」・としており・
「曜変」・「油滴」・「建盞」・などと・七種類へと分類し・特徴や当時の価値を記しています。
●「曜変」・・・●
★「建盞の内の無上也」・とされた曜変天目。桃山時代に一時・価値が下がるが・この曜変天目が天目中の最
高品として珍重され・「万疋」・(一疋は十文)・と莫大な金額がつけられていた。
◆「曜変天目」・(国宝・静嘉堂文庫美術館)。
●「油滴」・・・●
★天目のうち・「第二の重宝」・とされている。曜変とともに建盞とは別に項目が立てられており・異例のも
のであったことが分かる。曜変よりは数があるとされ・「五千疋」・の値が記されている。
◆「油滴天目」・(重美・根津美術館)。
●「建盞」・・・●
★曜変・油滴・烏盞と同じく建窯で造られたものと記されている。油滴のような星があると記されており・現
在の禾目天目をさしていると考えられる。値は・「三千疋」。
◆「禾目天目」・(林原美術館)。
●「烏盞」・・・●
★建盞と同じ土・釉薬で中国の盞・(浅い器の意)・の形をしており・当時の茶会記・拝見記などにその名は
出てこないため・実際にどのようなてんもくであったかは不明。
●「能皮盞」・・・●
★鼈盞と同じく・吉州窯で焼かれた二重掛けの天目で・花鳥などの文様がないものをさす。「代やすし」・と
されている。
◆「玳玻盞」・(東京国立博物館)。
●「鼈盞」・・・●
★建窯で焼かれた建盞ではなく・吉州窯で焼かれた天目で黄褐色と黒色の釉薬を二重掛けしたもの。そのうち
・「花鳥いろいろの紋あり」・として花・龍・文字などをあらわしたものをさす。値は「千疋」・と記され
ている。
◆「玳玻盞散花文天目」・(国宝・相国寺)。
●「天目」・・・●
★黒釉のうえに黄灰釉をかけた灰被天目が上物と記されており・現在の・「天目」・の意味とは異なり・黒釉
だけの天目をさしたと推測される。
◆「灰被天目」・(静嘉堂文庫美術館)。

●●「同じ建窯で焼かれた・曜変・油滴・禾目」・・●●
★こちらはすべて建窯・(現・中国福建省建陽県の末吉鎮にあった宋時代の古窯)・で焼かれたもので・その
ため健盞の名があります。それぞれ・「地いかにも黒く」・「地ぐすりいかにもくろくして」・「地くすり
くろく」・と・健盞の特徴である黒い胎土・(釉薬)・が挙げられています。曜変天目の特徴は・瑠璃色の
星形の斑文が一面にあり・種々の色が混ざって・綿の様な釉がある・と記されています。また・油滴天目は
・薄紫色の白っぽい星形の斑文が内側にも外側にもある・としていて・いずれも現在の分類と同じ定義です
。逆に・「建盞」・と挙げられるものには・油滴の様な星のあるものもある・としていて・現在の禾目天目
にあたると考えられます。この時代・「建盞」・という言葉には・「建窯で焼かれた盞」・という意味の他
に・いわゆる禾目天目を意味していたことがわかります。
●「曜変」・・・●
★こき瑠璃・うすき瑠璃の星・ひたとあり。又・黄色・白色・こくうすき瑠璃なとの色ゝ混しりて・錦のやう
なる・くすもりもあり。
◆「曜変天目」・(国宝・静嘉堂文庫美術館)。
●「油滴」・・・●
★うす紫色の・白けたる星・内外にひたとあり。
◆「油滴天目」・(重美・根津美術館)。
★油滴天目には内側だけでなく・外側にも高台際までびっしりと斑文がある。
●「建盞・(禾目)」・・・●
★白金の如くきんはりして・おなしく油滴の如く星のあるもあり。
◆「禾目天目」・(林原美術館)。

●●「吉州窯で焼かれた・黄と黒の天目」・・・●●
★吉州窯・(現・中国江南省吉安市永和鎮にあった宋・元時代の古窯)・で焼かれた鼈盞・と・能皮盞・(玳
玻)・盞は・いずれも黄白色のやわらかい胎土に・釉薬を二重掛けして・鼈甲様の色調を呈するものです。
『君台観左右帳記』・では・花鳥などの文様があるものを鼈盞・ないものを能皮盞としていますが・現在で
はその区分も曖昧になり・すべて能皮・(玳玻・玳皮)・天目と呼ばれることが多くなっています。吉州窯
では木の葉を黒釉に焼き付け・木の葉文様をあらわした平椀も多く作っており・室町時代の史料や後の茶会
記などに天目として登場しませんが・伝来する過程で・「木の葉天目」・の名となりました。
●「鼈盞」・・・●
★くすり黄色にて・黒きくすりにて・花鳥いろいろの紋あり。
◆「玳玻盞散花文天目」・国宝・相国寺。
★牡丹折枝が2枝背中合わせに付いた散華の文様が15個施されている。
●「能皮盞」・・・●
★くすり黄に飴色にて・うす紫の星・内外にひりとあり。
◆「玳玻天目」・重文・サンリツ服部美術館。
●●「建盞に上回った・「天目」・の価値」・・・●●
●「天目」・・・●
★伝来する過程で・大きく価値が変わったのは・『君台観左右帳記』・で・「将軍家の御用にないもの」・と
された・「天目」・です。室町時代の・「天目」・に含まれていた灰被天目をはじめ・白天目・黄天目・蓼
冷汁天目などでしたが・その価値が高まったことが・侘び茶の確立されつつあった天正十六年前後に成立し
たとされる・『山上宗二記』・に記されています。この本では・天目の項が茶碗より前に書かれていて・天
目が茶碗より格の高いものであることを示し・さらに建盞を・「代物カロキモノ也」・として低く位置付け
ています。これにより・茶道具としての灰被天目などが茶人に多く伝来しました。一方で江戸時代以降・「
建盞」・は室町将軍家の御物であったことにより・大名物として再評価され・武家大名家の宝庫に収めれれ
ていくことになります。現在・国宝に指定されている天目五点が・曜変天目三点・油滴天目一点・玳玻天目
一点から成るのは・この再評価の所以といえるのでしょう。
★つねの如し。灰被を上とする也。
◆「灰被天目」・(重美・永青文庫)。

●「単に唐物茶碗であるだけではなく、将軍家の茶と縁の深かった天目」・・・●

ー”ここより”ー
■■数寄のこころー「私のなかの茶の湯」・・・■■
●●「古きを温ね・新しきを知る名残の茶事」・・・●●
**”林屋晴三(東京国立博物館名誉会員)/選=筒井紘/料理・茶室協力=新宿柿傅”**
◆濃茶席に掛けられた・利休作・「竹二重花入」。
◆濃茶席の茶碗は・「長次郎の赤」・利休在判。
◆茶入は・「瀬戸玉川手」・(遠州の歌銘・佐保山とある)。
◆床は井上有一の・「月」。
◆花入は・辻村史朗の・「伊賀丸壺」。
◆主茶碗は楽吉左衛門の・「焼貫黒楽茶碗」。
◆他・・・・・。

●●「上記に一括」・・・●●

●●「同」・・・●●
|
■■『茶道誌』・・・■■ ●●『なごみ』・・・●● **”(2008年2月・通巻第338号)”** ■■『特集』・・・■■ ●●『唐物茶碗の至宝・「天目」・への招待』●● **”(約・38頁) ”** ★鎌倉時代・中国の禅院から喫茶法とともに・日本に持 ち帰られ・かの国への憧憬とともに・唐物として高く 高く賞翫された陶磁器であります。 その夢の跡をいまに伝えるのが天目です。 将軍家から近代数寄者まで・数え切らない人々を魅了 した天目をご覧いただきます。 ★七色の光彩を放ち・世界に3点とも4点とも伝え られる。 ◆「曜変天目」。 ・国宝。 ・静嘉堂文庫美術館。 ■発行日=平成20年2月1日。 ■発行所=株式会社・淡交社。 ■サイズ=18×25.5cm。 ■定価=840円。 ■状態=美品。 ●表紙に・多少の・キズ・ヤケが有ります。 ●本誌内に・多少の・ヤケが見えますが ●大きなダメージは・無く ●年代的には・良い状態に思います。 ◆◆注意・・・◆◆ ★発行日より・経年を経て下ります。 コンディションに係らず・古書で有る事を 充分に御理解の上・御入札下さい。 ★神経質な方は入札をご辞退下さい・・!! ●全・128頁・・・!! ●特集の・・・!! ◆「天目・への招待」・は・約・38頁。 ●蒐集・資料などの・参考に・・・!! ●探されていた方は・この機会に・・・!! ●以下・詳細をご覧ください・・・!! ◆掲載案内は・抜粋し掲載して下ります。 ◆掲載内容は・Q&Aより・問い合わせ下さい。 ◆数字記載は目視です・間違いは御容赦下さい。 ●掲載を抜粋紹介し・「タイトル」・と致します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ―”特集”― ■■『唐物茶碗の至宝・「天目」・への招待』■■ **”(約・38頁) ”** ―”「天目」への招待・①・拝見・天目の至宝”― ●●『国宝・曜変天目を語る』・・・●● **”対談”** ―”山下裕二さん・(美術史家)・× 長谷川祥子さん・(静嘉堂文庫美術館学芸員)”― ★「天目」・と耳にして・多くの人が思い描くのが・「 稲葉天目」・こと・国宝の曜変天目ではないでしょう か。 室町時代から時代を超えて人々を魅了し続けてきたこ の曜変天目が公開されると聞き・美術史家の山下裕二 さんが静嘉堂文庫美術館を訪ねました。 **”用語解説”** ◆1・曜変天目。 ◆2・岩崎小彌太。 ◆3・稲葉家。 ◆4・東山御物。 ◆山下裕二。 ◆5・君台観左右帳記。 ◆長谷川祥子。 ◆6・福建省の建窯。 ◆7・大正名器鑑。 ―”「天目」への招待・②・茶の湯の古典に学ぶ”― ●●『天目へ入門』・・・●● **”監修=竹内順一(東京芸術大学美術学部教授)”** ★室町時代・時の権力者たちは中国から海を越えて渡っ てきた美術品を・「唐物」・として愛し・その収集に 力を注ぎます。 天目もそのひとつ。 唐物は莫大な数にのぼり・吟味され・格付けされ・整 理され・その集大成が座敷飾りの故実書・『君台観左 右帳記』・に結実します。 天目の分類の範となった・この巻子から・「天目とは 何か」・を探ります。 ◆「曜変天目」。 ・国宝。 ・静嘉堂文庫美術館。 ―”天目の三条件”― ◆1・すぼまってから外に反る鼈口。 ◆2・漏斗状に開いた腰部。 ◆3・胎土を露わにした低い高台。 ●天目は色ではなく・形をあらわしていた。 ●「天目とは形のこと」・・・● ★天目という器だけでは未完成なもの。 天目台に載って・初めて完成した姿となる。 ◆「灰被天目」・「尼崎天目台」。 ・徳川美術館。 ★名物の天目台が残っている貴重な類例の天目。 ◆禅院茶礼の伝統の形式を伝える建仁寺の・「四 つ頭茶会」・で用いられる天目と天目台。 ●「天目は七種に分けられていた」・・・● ★『君台観左右帳記』・では・現在・天目と呼びならわ しているものをまとめて・「土之物」・としており・ 「曜変」・「油滴」・「建盞」・などと・七種類へと 分類し・特徴や当時の価値を記しています。 ―”曜変”― ★「建盞の内の無上也」・とされた曜変天目。 桃山時代に一時・価値が下がるが・この曜変天目が天 目中の最高品として珍重され・「万疋」・(一疋は十 文)・と莫大な金額がつけられていた。 ◆「曜変天目」。 ・国宝。 ・静嘉堂文庫美術館。 ―”油滴”― ★天目のうち・「第二の重宝」・とされている。 曜変とともに建盞とは別に項目が立てられており・異 例のものであったことが分かる。 曜変よりは数があるとされ・「五千疋」・の値が記さ れている。 ◆「油滴天目」。 ・重美。 ・根津美術館。 ―”建盞”― ★曜変・油滴・烏盞と同じく建窯で造られたものと記さ れている。 油滴のような星があると記されており・現在の禾目天 目をさしていると考えられる。 値は・「三千疋」。 ◆「禾目天目」。 ・林原美術館。 ―”烏盞”― ★建盞と同じ土・釉薬で中国の盞・(浅い器の意)・の 形をしており・当時の茶会記・拝見記などにその名は 出てこないため・実際にどのようなてんもくであった かは不明。 ―”能皮盞”― ★鼈盞と同じく・吉州窯で焼かれた二重掛けの天目で・ 花鳥などの文様がないものをさす。 「代やすし」・とされている。 ◆「玳玻盞」。 ・東京国立博物館。 ―”鼈盞”― ★建窯で焼かれた建盞ではなく・吉州窯で焼かれた天目 で黄褐色と黒色の釉薬を二重掛けしたもの。 そのうち・「花鳥いろいろの紋あり」・として花・龍 ・文字などをあらわしたものをさす。 値は「千疋」・と記されている。 ◆「玳玻盞散花文天目」。 ・国宝。 ・相国寺。 ―”天目”― ★黒釉のうえに黄灰釉をかけた灰被天目が上物と記され ており・現在の・「天目」・の意味とは異なり・黒釉 だけの天目をさしたと推測される。 ◆「灰被天目」。 ・静嘉堂文庫美術館。 ●「同じ建窯で焼かれた・曜変・油滴・禾目」・・● ★こちらはすべて建窯・(現・中国福建省建陽県の末吉 鎮にあった宋時代の古窯)・で焼かれたもので・その ため健盞の名があります。 それぞれ・「地いかにも黒く」・「地ぐすりいかにも くろくして」・「地くすりくろく」・と・健盞の特徴 である黒い胎土・(釉薬)・が挙げられています。 曜変天目の特徴は・瑠璃色の星形の斑文が一面にあり ・種々の色が混ざって・綿の様な釉がある・と記され ています。 また・油滴天目は・薄紫色の白っぽい星形の斑文が内 側にも外側にもある・としていて・いずれも現在の分 類と同じ定義です。 逆に・「建盞」・と挙げられるものには・油滴の様な 星のあるものもある・としていて・現在の禾目天目に あたると考えられます。 この時代・「建盞」・という言葉には・「建窯で焼か れた盞」・という意味の他に・いわゆる禾目天目を意 味していたことがわかります。 ―”曜変”― ★こき瑠璃・うすき瑠璃の星・ひたとあり。 又・黄色・白色・こくうすき瑠璃なとの色ゝ混しりて ・錦のやうなる・くすもりもあり。 ◆「曜変天目」。 ・国宝。 ・静嘉堂文庫美術館。 ―”油滴”― ★うす紫色の・白けたる星・内外にひたとあり。 ◆「油滴天目」。 ・重美。 ・根津美術館。 ★油滴天目には内側だけでなく・外側にも高台 際までびっしりと斑文がある。 ―”建盞・(禾目)”― ★白金の如くきんはりして・おなしく油滴の如く星のあ るもあり。 ◆「禾目天目」。 ・林原美術館。 ●「吉州窯で焼かれた・黄と黒の天目」・・・● ★吉州窯・(現・中国江南省吉安市永和鎮にあった宋・ 元時代の古窯)・で焼かれた鼈盞・と・能皮盞・(玳 玻)・盞は・いずれも黄白色のやわらかい胎土に・釉 薬を二重掛けして・鼈甲様の色調を呈するものです。 『君台観左右帳記』・では・花鳥などの文様があるも のを鼈盞・ないものを能皮盞としていますが・現在で はその区分も曖昧になり・すべて能皮・(玳玻・玳皮 )・天目と呼ばれることが多くなっています。 吉州窯では木の葉を黒釉に焼き付け・木の葉文様をあ らわした平椀も多く作っており・室町時代の史料や後 の茶会記などに天目として登場しませんが・伝来する 過程で・「木の葉天目」・の名となりました。 ―”鼈盞”― ★くすり黄色にて・黒きくすりにて・花鳥いろいろの紋 あり。 ◆「玳玻盞散花文天目」。 ・国宝。 ・相国寺。 ★牡丹折枝が2枝背中合わせに付いた散華の文 様が15個施されている。 ―能皮盞”― ★くすり黄に飴色にて・うす紫の星・内外にひりとあり。 ◆「玳玻天目」。 ・重文。 ・サンリツ服部美術館。 ●「建盞に上回った・「天目」・の価値」・・・● ―”天目”― ★伝来する過程で・大きく価値が変わったのは・『君台 観左右帳記』・で・「将軍家の御用にないもの」・と された・「天目」・です。 室町時代の・「天目」・に含まれていた灰被天目をは じめ・白天目・黄天目・蓼冷汁天目などでしたが・そ の価値が高まったことが・侘び茶の確立されつつあっ た天正十六年前後に成立したとされる・『山上宗二記 』・に記されています。 この本では・天目の項が茶碗より前に書かれていて・ 天目が茶碗より格の高いものであることを示し・さら に建盞を・「代物カロキモノ也」・として低く位置付 けています。 これにより・茶道具としての灰被天目などが茶人に多 く伝来しました。 一方で江戸時代以降・「建盞」・は室町将軍家の御物 であったことにより・大名物として再評価され・武家 大名家の宝庫に収めれれていくことになります。 現在・国宝に指定されている天目五点が・曜変天目三 点・油滴天目一点・玳玻天目一点から成るのは・この 再評価の所以といえるのでしょう。 ★つねの如し。灰被を上とする也。 ◆「灰被天目」。 ・重美。 ・永青文庫。 ★建盞とは異なり・たっぷりとした見込みも茶 人に好まれた。 桃山時代・天下人の茶碗にふさわしいものと して主役とされた。 ―”「天目」への招待・③・天目に魅せられた人たち”― ●●『いまに息づく天目の魅力』・・・●● ◆「曜変」・長江惣吉作。 ●「長江惣吉・さん・(陶芸家)」・・・● ★「曜変の再現」・という研究。 支えるのは曜変天目への敬意。 ◆「曜変」・長江惣吉作。 ●「桶谷寧・さん・(陶芸家)」・・・● ★曜変天目を生み出す方法論は・「焼き」・にあり。 ◆同じ釉薬を使いながら・焼成時間の差で・曜変 から金禾目まで変化した作品。 ・4点。 ◆他・・・・・。 ●「川島公之さん(古美術商・繭山龍泉堂)」・● ★定窯の天目。 建窯・吉州窯だけではない・鑑賞陶磁としての魅力。 ―”「黒定」・を代表する作品”― ◆「黒釉金彩蝶牡丹文碗」。 ・重要文化財。 ・個人。 ◆他・・・・・。 ―”(以下・白黒)”― ■■「天目と茶の湯」・・・■■ **”文=鈴木宗幹・(今日庵業躰)”** ●禅林の天目。 ●武家の喫茶・「書院の茶」。 ●「茶の湯」・の誕生。 ●天目から楽茶碗へ。 ■■「中国の喫茶文化と天目」・・・■■ **”文=長谷川祥子(静嘉堂文庫美術館学芸員)”** ●唐代に広がった黒釉陶磁。 ●建盞が流行した理由。 ●日本に請来された天目。 ●唐物天目への憧憬。 ―”名所の理由・茶道具の見かた”― ■■「掛物」・・・■■ **”小澤宗誠・(茶道家)”** **”(4頁・白黒)”** ★茶席の床には・書や絵を軸装した掛物が多く掛けられて います。 茶席で拝見する掛け物ならではの見所を紹介します。 ●掛け物の歴史。 ―”掛物の名所・各部名称”― ◆躙口から床を拝見。 ◆床前での拝見。 ◆本誌を拝見。 ―”数寄のこころ”― ■■「私のなかの茶の湯」・・・■■ **”林屋晴三(東京国立博物館名誉会員)”** **”選=筒井紘一”** **”料理・茶室協力=新宿柿傅”** **”(4頁カラー・5頁白黒)”** ★古きを温ね・新しきを知る名残の茶事 ◆濃茶席に掛けられた・利休作・「竹二重花入」。 ◆濃茶席の茶碗は・「長次郎の赤」・利休在判。 ◆茶入は・「瀬戸玉川手」 ・遠州の歌銘・佐保山とある。 ◆床は井上有一の・「月」。 ◆花入は・辻村史朗の・「伊賀丸壺」。 ◆主茶碗は楽吉左衛門の・「焼貫黒楽茶碗」。 ◆他・・・・・。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ■入力のミスは・ご容赦下さい。 ■他の出品も・是非御覧下さい。 ■商品詳細文の転用は堅くお断り致します。 ■入札案内・・・■ ●状態はすべて点検済ですが ●見落し等が無いとは言えません。 ●見解の相違も御座います。 ●御了承・御理解の上・入札下さい。 |
■■支払詳細■■ ●かんたん決済。 |
|
|
■■送料の案内■■ ●185円。 ●クリックポスト。 ・(日本郵便)。 ・(1回1落札)。 ●簡易包装。 ・(包装指定は別途料金)。 ●落札金額に関わらず同一の包装と ●させて頂きます。 |
|
|
|
■■注意■■ ●質問は必ず事前にお願い致します。 ●落札後のクレームはお受けできません。 ●落札日より7日以内に必ず決算下さい。 ●7日以内に振込み確認出来ない場合は落札者都合 ●のキャンセルとして処理させて頂きます。 ●取り置の場合でも、最初の落札日より7日以内に必 ●ず決済下さい。 ●いかなる場合でも決済後に・一度発送致します。 ■■要注意■■ ●入札の取消はいかなる場合でも不可能です ●質問欄での取消依頼もお受けできません。 ●落札後は取引ナビにて詳細を連絡させて頂きます。 ●電話での連絡はお受けできません。 ●上記事項を充分に御理解の上での入札とさせてき頂 ●ます。 ■商品詳細文の転用・盗用は堅くお断り致します・! |
||
+ + + この商品説明は オークションプレートメーカー2 で作成しました + + +
No.213.002.002