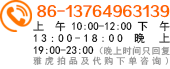商品参数
- 拍卖号: c1125493666
开始时的价格:¥9922 (200000日元)
个数: 1
最高出价者:
- 开始时间: 2024/6/13 17:12:02
结束时间:
提前结束: 有可能
商品成色: 二手 - 自动延长: 会
日本邮费: 卖家承担
可否退货: 不可以
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
約200~250年前に作られた長与三彩小皿(五枚揃)です。
口径は五枚共に9.5cmでほぼ同じですが厚み・高台径・高さなどは微妙に違いがあります。
口径:9.5cm、高さ:2.3cm~2.7cm、高台径:4.8cm~5.4cm。
多少の虫食い、ホツなどはありますが時代を考えると良い状態が保たれています。
(ご参考...長与町ホームページより引用)
16世紀末の肥前地方での焼物界の様相は、唐津系陶器窯の一部ではそれまでの陶器に換わって磁器が焼かれるようになり、その傾向は17世紀になるとますます助長されて、量産化体制に備えての窯場の整備が行われるようになった。これはヨーロッパ社会がこれまでの中国陶磁器に換わって、日本にその代用を求めるようになったからである。肥前地方の領主たちは利益を得るために積極的にその転換を図ったが、当時はまだ日本人の生活では磁器の使用は一般的には浸透しておらず、そのために肥前の窯場では藩の保護を受けた磁器窯と、日本人の生活食器を焼く陶器窯の集団が存在するようになった。特に燃料の薪を必要とするところから磁器窯は優遇され、陶器窯は地方へ分派する傾向を示していった。町内の嬉里郷字田尾に窯跡を残している長与皿山は、そのような背景のもとに開かれたのである。
江戸時代に大村藩が編纂した『大村郷村記』によると、寛文7年(1667)に浅井角左衛門・尾道吉右衛門・山田源右衛門・尾道長左衛門の願い出によって始まっている。ちなみに浅井角左衛門とは鯨組の頭領として名高い2代目深沢儀太夫勝幸のことである。この時に焼かれた製品については陶器・磁器のいずれかはまだ判然としない部分があるが、操業期間については同じ『郷村記』の中に記されている元禄9年(1696)と同11年の2回にわたって、焼物生産の生命とも言うべき原料の中尾土を諫早領の現川窯の陶工たちに譲渡していることからおよそ30年間の操業であったろう。
その後正徳2年(1712)には同じ大村領内の波佐見から太郎兵衛がきて窯を再興し、18世紀中頃には窯の経営も順調となり盛んに藩外にも売りさばかれるようになったが、19世紀に入ると焼物の値段が下がったために窯の経営は苦しくなり、文政3年(1820)に生産を中止した。この時期には大坂で人気があった「お笹紅」の容器を注文で作ったり、安永4年(1775)には伊予大洲藩領の砥部に白磁焼成の指導のために陶工を派遣している。また長与焼を代表する「長与三彩」の製品もこの時期に作られたのである。
長与三彩についてはこれまで『郷村記』に寛政4年(1792)に長与村の市次郎が珍しい焼物を焼いたという記載から、これが長与三彩の始まりであると言われてきたが、平成3年(1991)に熊本県天草の上田家に保管されていた古文書の、『近国焼物大概帳』が紹介されてこのことを補強することとなった。これは寛政8年(1796)に天草郡高浜村焼物師伝九郎と同村庄屋の上田源作から、島原大横目の大原甚五左衛門に提出されたものの写しであるが、その中で長与皿山についての文中に「此所チャンパン焼物師壱人大村より御扶持頂戴帯刀御免之仁有之』とある。チャンパンとはチャンパあるいはチャボと呼ばれて現在のヴェトナム地方を指す言葉で、そこは16世紀後半から17世紀前半にかけて朱印船貿易で日本にもたらされた「交趾三彩」と呼ばれる焼物と深い関わりがあるところである。この三彩の焼物は日本で好き者に珍重されたため、京焼や四国の源内焼で盛んに模した三彩の製品が作られた。古文書の年号は『大村郷村記』に記された寛政4年(1792)からわずか4年後に書かれたものであり、これらのことから推察すると長与三彩は、交趾三彩の技術をもとにして出現したことが十分に考えられる。
弘化2年(1845)には再興窯を開いた太郎兵衛の子孫になる渡辺作兵衛によって再再興が行われたが、その操業は小規模で安政6年(1859)には閉窯している。製品には白磁染付類や当時長崎で焼かれていた亀山焼(1807〜1865操業)や鵬ヶ崎焼(1823〜1852操業)、あるいは古いところの現川焼(1691〜1749頃操業)などを模したものなどがある。伝承によれば明治期に土管や水がめ類を焼いたと言われるが、現在までのところではそれらを確証する根拠はまだ無い。
江戸時代に大村藩が編纂した『大村郷村記』によると、寛文7年(1667)に浅井角左衛門・尾道吉右衛門・山田源右衛門・尾道長左衛門の願い出によって始まっている。ちなみに浅井角左衛門とは鯨組の頭領として名高い2代目深沢儀太夫勝幸のことである。この時に焼かれた製品については陶器・磁器のいずれかはまだ判然としない部分があるが、操業期間については同じ『郷村記』の中に記されている元禄9年(1696)と同11年の2回にわたって、焼物生産の生命とも言うべき原料の中尾土を諫早領の現川窯の陶工たちに譲渡していることからおよそ30年間の操業であったろう。
その後正徳2年(1712)には同じ大村領内の波佐見から太郎兵衛がきて窯を再興し、18世紀中頃には窯の経営も順調となり盛んに藩外にも売りさばかれるようになったが、19世紀に入ると焼物の値段が下がったために窯の経営は苦しくなり、文政3年(1820)に生産を中止した。この時期には大坂で人気があった「お笹紅」の容器を注文で作ったり、安永4年(1775)には伊予大洲藩領の砥部に白磁焼成の指導のために陶工を派遣している。また長与焼を代表する「長与三彩」の製品もこの時期に作られたのである。
長与三彩についてはこれまで『郷村記』に寛政4年(1792)に長与村の市次郎が珍しい焼物を焼いたという記載から、これが長与三彩の始まりであると言われてきたが、平成3年(1991)に熊本県天草の上田家に保管されていた古文書の、『近国焼物大概帳』が紹介されてこのことを補強することとなった。これは寛政8年(1796)に天草郡高浜村焼物師伝九郎と同村庄屋の上田源作から、島原大横目の大原甚五左衛門に提出されたものの写しであるが、その中で長与皿山についての文中に「此所チャンパン焼物師壱人大村より御扶持頂戴帯刀御免之仁有之』とある。チャンパンとはチャンパあるいはチャボと呼ばれて現在のヴェトナム地方を指す言葉で、そこは16世紀後半から17世紀前半にかけて朱印船貿易で日本にもたらされた「交趾三彩」と呼ばれる焼物と深い関わりがあるところである。この三彩の焼物は日本で好き者に珍重されたため、京焼や四国の源内焼で盛んに模した三彩の製品が作られた。古文書の年号は『大村郷村記』に記された寛政4年(1792)からわずか4年後に書かれたものであり、これらのことから推察すると長与三彩は、交趾三彩の技術をもとにして出現したことが十分に考えられる。
弘化2年(1845)には再興窯を開いた太郎兵衛の子孫になる渡辺作兵衛によって再再興が行われたが、その操業は小規模で安政6年(1859)には閉窯している。製品には白磁染付類や当時長崎で焼かれていた亀山焼(1807〜1865操業)や鵬ヶ崎焼(1823〜1852操業)、あるいは古いところの現川焼(1691〜1749頃操業)などを模したものなどがある。伝承によれば明治期に土管や水がめ類を焼いたと言われるが、現在までのところではそれらを確証する根拠はまだ無い。